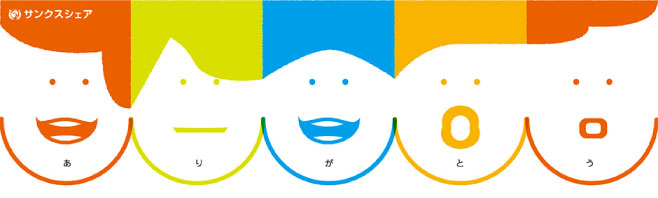KYOUKOU㊷報告
KYOUKOUU(強度行動障がい勉強会)第42回は、前回の髙村 壮士さんからのリレー推薦として、吉永 菜穂子さん(NPO法人それいゆセンター長)をお迎えしました。
1 タイトル 強度行動障がいとわたし(「強度行動障がいとわたし」シリーズ6回目)
2 日時 R7.11.8 13時00分~15時00分(その後講師と情報交換)
3 場所 CO-WORKING SALON 四季のいろ(博多区千代)
4 お話 吉永 菜穂子さん(NPO法人それいゆセンター長)
5 参加 会場参加 27 名 Zoom参加 15 名 (情報交換会 22 名)
6 内容
 今回の研修は、お子さんの支援にも経験が豊富な吉永さんから、それいゆさんの紹介も含めて、自閉症などの特性がある方への支援についてていねいに情報提供いただきました。
今回の研修は、お子さんの支援にも経験が豊富な吉永さんから、それいゆさんの紹介も含めて、自閉症などの特性がある方への支援についてていねいに情報提供いただきました。
その支援は、対象の方の特性を的確に把握することを大前提として、一貫したかかわりをすることで成し遂げられることを身に染みて実感することができました。そう感じることができたのも、ほぼネガティブなお話をされることなく、前向きに、そして、肯定的にものごとを考えられる吉永さんのお人柄が根底にあるからだと思いました。とかく、ネガティブな話になりがちなこの話題について、どう向き合っていくのかを自分自身振り返る機会ともなりました。
「わかっていると、許されるじゃないですか(^^)」
こうおっしゃった吉永さんの言葉が刻み込まれています。裏を返せば、知らないと支援ができません、もしくはしてはいけません、ということなんだと自分自身に言い聞かせました。最終的に、対象の方の100%を知ることはそう簡単にはできないのかもしれませんが、少なくとも『知ろう』とすることには常に向き合いたいと思った時間でした。
今回も、会場参加とzoom参加の方と新たなつながりもいただきました。このつながりを大切にしていきたいと思います。
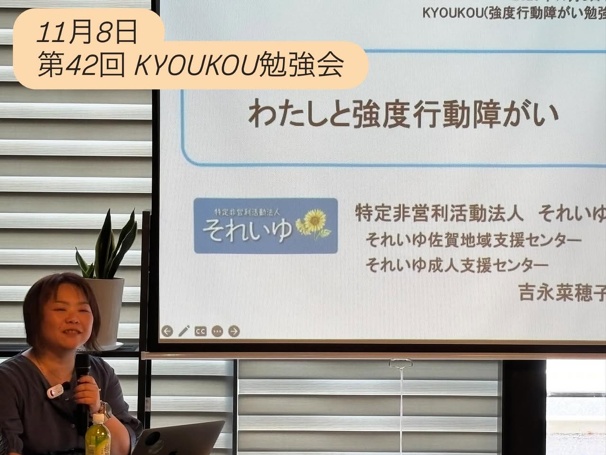
お話の詳しい内容は、どうぞ動画全編をご覧ください。
(動画ハイライト編)
※ 会員以外の方で、全編視聴を希望される方は、どうぞご一報ください。https://forms.gle/W4pYA5K8rCmzTGPY7
【ご参加いただいた方の感想】
- 14歳の息子、重度知的障害と右片麻痺ありの母です。先月に自傷が可哀想なくらい酷く、どうにかしなくちゃと、今回の勉強会のお知らせを知り、参加しました。前から療育やディの先生から視覚で理解できるカードを使って!と言われつつ、本人がどれだけ理解できているのか、分からない部分あり、めんどくさく感じていました。改めて視覚支援を丁寧に取り組んでみようと思いました。学校では1日のスケジュールは視覚的にされているでしょうが自宅では全くでした。今日は貴重なお話をありがとうございました。
- 今回Zoom参加でしたが、貴重な研修に参加させていただき、本当にありがとうございました。具体的に言葉かけは、簡潔に穏やかに落ち着いた声で1度に1つずつ行う事や「できたね」「ありがとうね」と自信を育てる言葉かけの大切さとそれぞれの障害特性の理解の大切さなど、沢山学ばせていただき心より感謝申し上げます。転職して約一年で、分からない事も多いですが、なるべく前向きな気持ちで働いていきたいと思っています。ありがとうございました。
- 最初の30分位は携帯での視聴だったので画面が小さくて、説明されている事が中々わからなかったのですが、パソコンでの視聴に出来てからはパワーポイント等の資料も良くわかるようになって細かく説明をして下さっているなーと感じました。ご家族の話から、本人と家族との葛藤等事例がより具体的に話されていたので内容としてはわかりやすかったと思います。強度行動障がいにおいて区分が5〜6と大変に見える人より3〜4のグレーゾーンの人の方が大変で課題が多いと言われていた事も、現場からの本当の声なのだろうと思いました。私の施設では強度行動障がいに該当するのは小学校低学年の児童なので、大人の場合や成人に近い年齢の対象者ではもっと支援が難しいのかなと思いました。ASDの特徴の理解やアセスメントが重要、最終的に自立を目標として取り組む事。個別の特性に合った支援が必要と言う事も自分の施設に置き換えて見た時に私を含め職員の経験や対応が適切かと言えない部分反省点でした。考えさせられる事が多かったです。
- 初めて勉強会に参加しました。視覚支援や構造化について、とてもわかりやすい言葉で説明していただき、強度行動障がいと言われる方々の理解にとても役立ちました。特に印象に残ったのは、「生まれつきの行動障がいはいない。行動障がいは、本人に適してない環境や支援によって生じたもの」とおっしゃったことでした。私は児童発達支援事業所に勤めていますが、行動障がいは子どもの特性ではないかと思い込んでいるせいで、私たち支援者の課題だと捉えることができていなかったように感じました。アセスメントからその方を知る大切さや、構造化によってバリアフリーになる等、勉強になることばかりでした。また、参加したいです。ありがとうございました。
- 避難訓練を毎月やっているというのが素晴らしいと思いました、どこの事業所も法定で決まったことしかやっていなくて、非常時に対応することは難しいと思っていましたので。
- 特性に合わせた支援については吉永先生のお話しの中にもありましたが、本人の言動に常に「なぜだろう?」と疑問を持ち、本人のことをよく理解すれば支援者側の心にも少し余裕が持てるし、より良い支援にも繋がっていくのではないかと思いました。また、一貫した支援や統一した支援が大事であるとのお話がありましたが、実際に支援の場で実践できているかというと複数の支援者で支援する現場においては個々の経験値の差や考えやスタンスの違いがあり、今の自身の職場においては難しい課題になっているなと考えさせられました。ですが、交流会の中でお話しさせていただく中でいきなり全ての課題を解決していくのではなく、まずは支援者側が本人の困った言動について決めつけせず何故だろうと考える機会を持つなど、出来ることからはじめていくこと、まさに支援者側もスモールステップですすめていくことの大切さにも気付かされました。今回も色々な方と繋がれてとても充実した時間を過ごすことが出来ました!吉永先生、サンクスシェアの皆様本日はありがとうございました!
- たくさん学べて楽しかったです。ありがとうございました!
- 強度行動障がいと係る現場を拝見できました。ありがとうございます。今後、弊社が必要とされた時に役立てたいと思います。
- 氷山モデルの考え方、障害特性の理解の大切さを再確認することができました。
きょうだいとしての視点、家族としての視点からのお話しはとても貴重でした。家族は家族の支援はできないと仰って(きっと上手に日頃関わっておられると思いますが)いたことに特に共感しました。家族の立場と支援者両方の立場をお持ちの方の現場の支援の難しさなどお聞きしてみたかったと思いました。これまでつながらないと思っていた方々につながることができて、とても貴重な時間となっています。吉永先生、貴重なお話しありがとうございました。サンクスシェアのみなさま、いつもありがとうございます。 - TEACCHプログラムのことを改めて学ぶ機会となりました。視覚支援、構造化、何より障害特性を理解していくことが適切な対応や生活を豊かにすることにつながることを学びました。私の生活介護の支援 現場でも、なかなか本人の特性を理解できず、十分な支援を行えていなく、職員も 疲弊している状態にあります。今回 吉永先生が教えていただいたことを現場の実践にしっかり勉強しながら取り組んでいけたら良い方向に向かっていくのではないかと気付きをいただきました。ありがとうございます。
- 「利用者のせいにするのをやめる」という言葉を忘れないように、その為に今回の研修の内容であった特性を知ることと、視覚的支援の活用をしていきたいと思いました。また、支援を進めていく中で、本人家族、支援者と一緒に考えてみんなが「ハッピー」になれる方法を求めていきたいと思いました。
- 強行の方や区分5.6の方の就労移行や一般就労のお話を聞き、自分自身の強行の方のイメージが施設入所に偏り過ぎていたことに反省した。様々な可能性にチャレンジできる勇気を頂きました。一方で、「それいゆ」のような構造化された広い施設や支援体制が身近な場所でも増えていくとよいと強く願います。
- 支援を行う中で、視覚支援という言葉をよく聞きます。『支援』とつくと、大変なことのように聞こえてきますが、分かりやすさ と置き換えると取り組みやすいと思いました。私たちが日常で目にする視覚支援は街中に溢れており、学習会後の道のり、改めて意識して道路を走っているとマーク、矢印、色…様々な支援があることを実感しました。改めて、支援する側の考えの押しつけではなく、利用する人の特性にあわせた、本当の意味での分かりやすさを追求する。そのためにも、一人一人に丁寧に関わっていきたいと思いました。また、吉永さんのお話は、支援に対する基本、初心に立ち返るお話でもありました。(ズレているかもしれませんが)視覚支援、分かりやすさを考え進めていくことは、相手を思う優しさにも通じるものがあるのかなぁと思いました。今回も、貴重なお話を聞くことが出来ました。ありがとうございました。
- 吉永さんのお話は、自閉症児者の特性がある人への支援のほぼ全体像をくまなく解説していただいたと思いました。専門的知識と理論を交え、さらに具体的な現場支援の実例をもとに、エッセンスを説明くださり大変わかりやすいお話でした。また、強度行動障がいのネガティブな部分はほぼなく、どのような行動障がいがあっても、的確なアセスメントをもとに、本人の状況を肯定的にとらえ、一貫して支援する揺るぎないポリシーに頭が下がる思いでした。言葉で言うのは簡単だけれど、日々の実践で続けていくことは並大抵のことではないと思います。きっと他の職員さんともていねいな情報共有を行い、視覚支援、環境調整を徹底しながら関わっておられる賜物だと思います。情報交換であまりお話はできなかったものの、なんらかの個別の相談でもお世話になりたいと強く思ったのでした。貴重な時間を過ごせたことを心より感謝します。
- 視覚支援と構造化について、とても興味深く学ぶことができました。視覚的な支援は、本人の不安を軽減し、「分かった・できた」という経験の積み重ねが自立や自己肯定感の向上につながることを再認識しました。また、支援者にとっても指示や制止の頻度が減り、支援が効率化するなど多くのメリットがあると感じました。具体的な事例を通して、肯定的な伝え方の重要性や、否定形ではなく「OK」を示す環境づくりの意義を学ぶことができました。福祉現場でも、必要に応じて視覚的支援を柔軟に取り入れることが本人の安定や支援の質向上につながると感じました。改めて、個々のアセスメントに基づいた支援設計の大切さを実感し、とても有意義な研修でした。
- 強度行動障がいの担当利用者はいないが、日々の業務の中で視覚から伝える事をしているがうまく相手に伝わらない事が多く感じていた。色々な方法を利用者に合わせて試していく事が大切だと改めて感じた。また、自立の為の支援について本人が出来る事まで手を出している可能性が高いと思い日々の業務の見直しも改めて必要だと感じた。
- KYOUKOUに参加。視覚支援、構造化に対しての考え方がとてもスッキリした。発達障害の方のバリアフリーという表現をされていたが、社会全体が視覚的にわかりやすくなることで、だれでもわかりやすい社会になるといいと感じた。
- 恥ずかしながらすべてのお話が新鮮で大変勉強になりました。先生のお人柄に触れさせていただき、改めて福祉の世界に入って良かったなと思いました。この世界の奥深さとやりがいを再認識することができました。これからも勉強させていただきます。誠にありがとうございました。
- 勉強会に参加し、長年にわたり当事者やご家族と関わってこられた吉永先生の経験と、揺るぎない信念のようなものを感じた。特に印象に残ったのは、「強度行動障がいは本人の中に生まれつきあるものではなく、環境や支援のあり方によって生じる二次的なもの」という言葉だった。その背景には、本人なりの理由や苦しさがあるのだと改めて気づかされた。また、氷山モデルのスライドを見ながら、私たちはどうしても“見えている部分”だけに目を向けがちであると感じた。表に現れる行動を“問題”として捉えるのではなく、その奥にある“助けて”というサインとして受け止める視点を持ちたいと思った。さらに、視覚支援や構造化の大切さについても学んだ。言葉で伝えるよりも「見てわかる形」で伝えることが、その人にとっての安心につながるということ。理解できることで不安が減り、できることが増えていく。そして、それは支援者にとっても支援がしやすくなるということを実感した。今回の学びを通して、今後も行動の裏にある思いや特性に目を向けながら、その人らしい生活を支えられる支援者でありたいと強く感じた。

福岡市東区で障がい福祉サービスに携わる人を育てる会社
合同会社サンクスシェア 2016年4月4日 創立